はじめに
ABOUT US住友商事マシネックスが向き合う社会
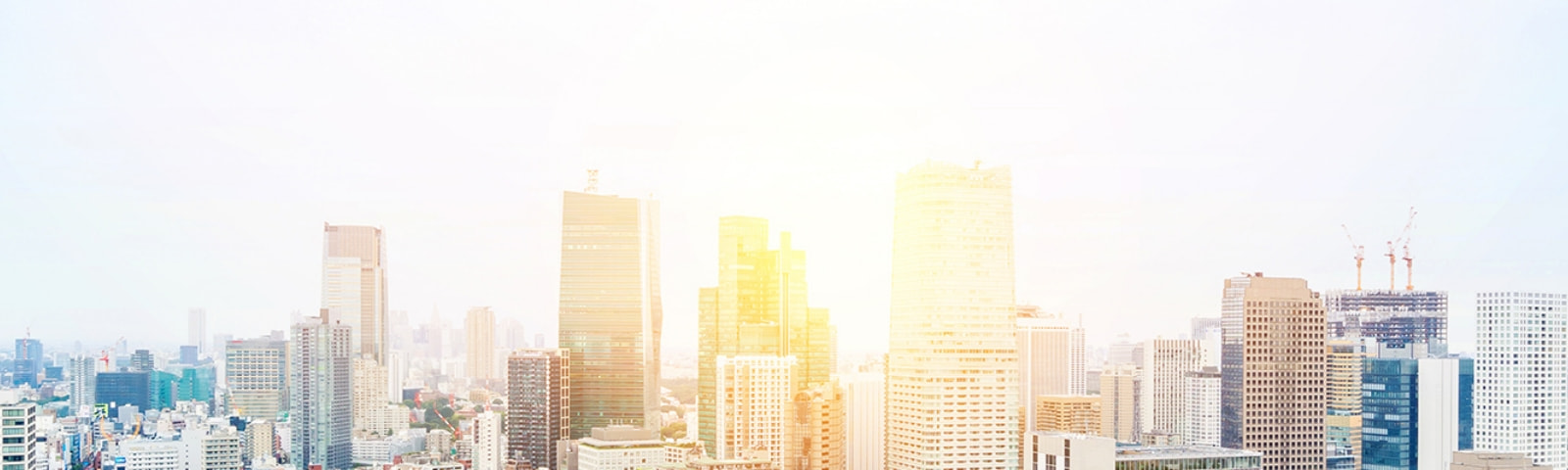
ABOUT US住友商事マシネックスが向き合う社会
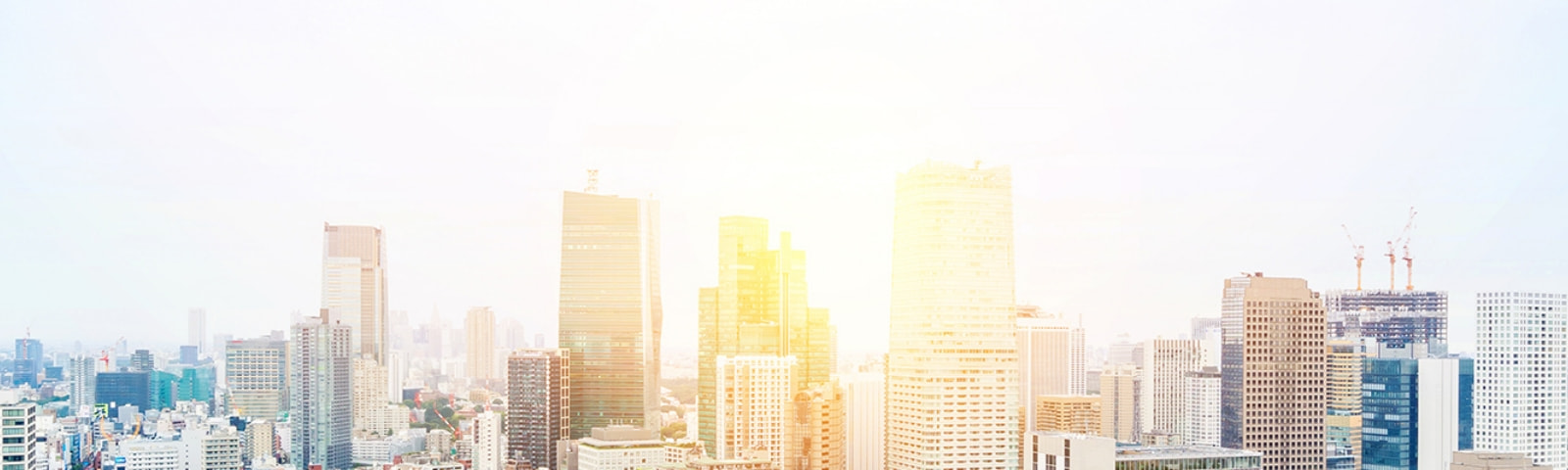
住友商事マシネックスのありたい姿
変わり続ける社会で、
人と社会とテクノロジーを繋ぐ。
21世紀は急速な技術革新と社会の変化の時代です。
目まぐるしい変化の中で、私たちは、持続可能な社会の実現に向けて、当社独自の機能を提供し、変化にいち早く対応できる社会づくりが求められています。
地球の未来、すべてがフィールド
顧客や社会が現在抱えている課題、将来に向けて先んじて取り組むべき分野に対して、これまで培ってきた、社会・産業インフラ分野での課題発見能力、ソリューション構築力を駆使し、あらゆる分野のテクノロジーにアクセスし、変化する社会構造の中で価値あるビジネスを共創しています。

これまで培ってきた、社会・産業インフラ分野
での課題発見能力、ソリューション構築力
顧客・パートナー
顧客・パートナーが有する
テクノロジー、新たな価値
01
DX
デジタルトランスフォーメーション
DXとSMX
昨今、様々な場面で耳にするキーワードであるDX。デジタル技術の浸透によって、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることを言います。私たちの事業領域に目を向けると、生産性向上、データ活用による新たな価値の発見、経営基盤の強化等、企業はDXを通じた変革の実行が求められており、非常に多くの企業が、DX推進を経営方針や事業方針に組み込んでいます。住友商事マシネックスでは、製造業をはじめ、社会・産業インフラに関わるすべての方にその課題をデジタルで解決する手段とその未来を提供しています。
次世代通信インフラ構築を通じたDXを推進
顧客・社会のDigital Transformationを実現する
住友商事マシネックスは、超高速・低遅延・多接続を可能とする5Gや次世代Wi-Fiをはじめとした通信インフラから、マルチプロトコルや生産ライン可視化ツールといったソリューションまで一気通貫で提供し、製造業が抱える課題の解決にデジタルの観点からアプローチしています。
現場力を生かして顧客のニーズをヒアリングし、企業や自治体等が最適な仕組みを構築し課題を解決できるよう支援します。


02
GX
グリーントランスフォーメーション
GXとSMX
GXとは、化石燃料ではなく太陽光発電などのクリーンエネルギーを利用し経済社会システムや産業構造を変革して温室効果ガスの排出削減と産業競争力向上の両立を目指す概念です。世界中で緊急課題となっている地球温暖化対策も企業責任の一つに挙げられ、多くの企業が事業や構造の見直しに取組んでいる中、地球規模の課題解決に寄与するテクノロジーの提供を行っています。
私たちが実現するGX
カーボンマネジメントの取組
社会システム単位での脱炭素イノベーションの取組
当社の事業フィールドの多くを占める製造業をはじめ、社会全体でGX(Green Transformation) に資する取組が求められています。住友商事マシネックスでは、既存のエネルギー効率化技術、電化技術(需要の創出)、再エネ技術活用、脱炭素イノベーション、といった社会システム単位でのカーボンマネジメントに取組んでいます。

バイオコークスの社会実装に向けて
鉄鋼業界におけるCO₂排出量削減を目指す
バイオコークスとは、光合成に起因するほぼ全ての植物から形成できるカーボンニュートラルな固形燃料であり、製鋼工程で使用される燃焼用石炭コークスからの代替燃料として期待されています。鉄鋼業界におけるCO2排出量の削減のみならず、現状廃棄されている食品残渣、廃棄衣料といった未利用バイオマス資源を原料とすることにより食品ロスをはじめとする様々な廃棄物の問題解決にも寄与することが見込まれており、産学連携のもと、バイオコークスの社会実装によりバイオマス資源と産業界の地域循環共生圏の創造を目指します。


03
共創の実現
コ・クリエーション
共創とSMX
共創とは、企業が様々なステークホルダーと協働しながら、事業活動を行い、新たな価値を創造することを意味する概念です。多くのステークホルダーと関わり合うことで、これまでにはなかったニーズを発見し、自社だけでは生まれなかったアイデアやソリューションを発想・提供することが可能となります。住友商事マシネックスではこれまでの60年のあゆみで培った顧客・パートナーとのつながりを通じて、社会全体のイノベーションを目指します。
私たちが実現する共創
名古屋共創ラボ(SMX OPEN INNOVATION LAB)
製造現場のDXをカタチにしていく
産業の集積地である中部圏/名古屋に開設した「共創ラボ」では、当社としてのソリューション構築及び様々なパートナー各社様との実証実験や、イベント・プログラム開催によって「共創」深化を行う場として、各本部・各部署における個別取り組みを通じた活用を推進しています。



